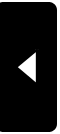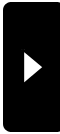2008年10月26日
最終章 二期会と銀鉄、公演見ました
二期会のオペラ公演と銀河鉄道のミュージカル公演を、比較して述べています。
いよいよ、最後のブログになりました。
「舞台監督・舞台進行・制作体制」
もっとも複雑で、その団体ごとの個別の事情が現れ、なかなか正論だけでは解決しない問題がたくさんある項目です。
ただ、それは以前のブログにも書きましたが、東京などで行われている、プロ出演者とプロスタッフによる舞台公演にしても、より大きな予算が動き、スポンサーもあり、収益とかより大きな名声・プライドなどが複雑に絡まりあっています。
なので、地方だから、みんなそれぞれ別の職業を持っているから・・などの要素は、多かれ少なかれ、世界中のどんな「ケース」でも持っている要素です。
それぞれの「事情」はあるにせよ、出演者がアマチュアでも職業演奏家でも、公演そのものを職業としている人にせよ団体にせよ、舞台にかけられた作品は、その背景事情を加味することなく、気にすることなく、舞台作品としての評価、批評はあるべきである。そう思っています。
では、 ■■舞台監督・舞台進行・制作体制■■ です。
まずは、舞台監督ですが、舞台監督という職域は、舞台の分野によってその仕事はかなりの専門性を要求されます。
コンサート関係では、英語での呼び方としての「ステージマネージャー」と呼ばれています。
なので、パンフレットのスタッフ一覧を見ると、二期会さんも銀鉄さんも、さすがにこの部分はプロに任せています。
わたしは、すべての舞台行事に「舞台監督」「ステマネ」は配置されるべきポジションだと思っています。
最低限、この職域に「人件費」という予算立てをしない舞台はよくない、と思っています。
予算立てをしないまでも、その職域が持つ役割を持った明確な人物を立てる、ということが、観客に不要なストレスや違和感、「田舎っぽい」とか「なんか、段取りが悪いなぁ」とかの感覚を与えることを防ぎます。
『そんなにかしこまらなくても、大上段に言わなくても、少し段取りが悪くても、それが手作り感があるし、団体の雰囲気も伝わるから、それでいいんですよ』という話は、よく聞きます。
わたしは、それは認めません。舞台の神様に失礼です。そう考えています。
舞台というのは「板の上」と呼ばれ、舞台袖から本舞台に入る前には一礼をし、リハや場当たりが終わって舞台を降りるときには、また舞台に向かって一礼をする。
ひとの立ち居振る舞い、所作が綺麗でかっこよかったり、ぴったりしていることを、「イタに付いてるなぁ」と言いますが、これは、舞台の上で足がしっかりと舞台の板について、重心が座っており見た目に安定感があり美しい姿の語源から来ていると言われています。
こういった文化は、日本舞踊など日本の古典舞台の世界ではまだ生きています。
若いころに日本舞踊の現場に行く時には、ほんとうに身が引き締まって、継続され伝承されて来た日本の「文化に触れている」という感覚を持ったものです。
そういう認識を持っている者として、舞台監督にちゃんと予算を置き、パンフレットにも名前を記載する。このふたつの団体は、きちんと舞台を作り続けている老舗ならではの体制だと思いました。
二期会
二期会さんの舞台監督は福山の方で(20年前、一緒に仕事をさせていただいたときにはそうでした)、もうずいぶん大ベテランの方です。西日本において貴重な存在の方です。この分野で後継者は育っていられるんでしょうか・・。今回のパンフレットには「舞台監督助手」というクレジットで3名の方の名前が記載されています。このうちひとりでも、舞台監督の方の事務所の若い方であれば、舞台業界にとって明るいことです。
また、二期会さんのパンフには、「大道具製作・操作」という項目があり、高松の舞台会社の名前がクレジットされています。小道具として、舞台監督さんの事務所名がクレジットされています。オペラの舞台監督は、オペラの知識が必要です。本人の勉強も必要です。高松では、オペラの舞台監督ができる方は、わたしの知る限りいません。
ですから、パンフレットからだけ判断すると、この二期会さんの体制はさすが20数年の積み重ねで、質と手間と予算のバランスを磨いてきたものなんだなぁと思わせるものです。
オペラの知識が必要な舞台監督のポジションは、西日本で活躍されるベテランを。舞台セットの製作は、十年くらい前でしょうか、高松の音響・舞台製作会社から独立した若手が始めた舞台の会社に発注。小道具は、バレエやオペラを数多く長年手がけている舞台監督の事務所から調達。また、衣裳の主だったものは日本最大の東京衣装から入手し、地元の服装学院さんの協力を得ている。いいバランスですね。
もちろん、このスタッフ一覧の最後にクレジットされている「制作 四国二期会制作部」という項目の持つ大きな意味もあります。練習会場の予約から、出演者への連絡、楽譜のやりとり、衣裳のやりとり、オーケストラへの連絡、依頼しているプロの方々との連絡・・・プロに依頼できない部分の手作業・・・・今回出演されていない会員、先生方の手伝い・・・そして、もっとも大切な協賛依頼とチケット販売・・・・それらの細かな作業と配慮がなくては、最終的に幕は上がりません。
これらのことはパンフレットから想像できますが、その上で、ひとつだけ気になることを・・。
最初の頃に触れましたが、天国の場面でのひとりひとりの動きの中で、あまりにも素人の突っ立ちや意味のない手振りなどが目立った点です。「声が聞こえない」という訓練の必要なことではなく、この舞台上の「立ち居振る舞い」の部分は、舞台監督を含めた制作サイドの配慮、取組みで防げたのではないか、ということが、とても気になりました。
誰かがどこかで、「これで・・仕方ない・・・・」とあきらめたのではないか。「未必の故意」という用語が、よく犯罪もののドラマで使われていますが、リハーサルとか、前日のゲネプロなどでも見えていたはずなのに?と思ってしまいました。
これは、誰かのせい、という犯人さがしの話をしているのではなくて、これだけの人数が動く舞台をつくりあげる体制として、「演出助手」というポジションが必要だったのではないかと。稽古場では、どなたかがその役割をやっていたのかも知れませんが、明確に必要なポジションとして置くべきではなかったのか、と。そんなことを見ている途中から強く思いました。
もしかすると、「舞台監督助手」にある3人の方のどなたかが、その役割を担っていたのかも知れませんが・・。
また、スタッフ一覧には、練習時にピアノを弾くみなさんの名前が5人クレジットされていて、みなさんが集まり生演奏付きで練習することの大変さが窺い知れる記載ですね。
銀河鉄道
銀河鉄道さんのスタッフ一覧を、二期会さんの項目と比較してみると、「制作」で2名、「制作管理」で1名、「オフィス」で1名とクレジットされています。また、「振り付け助手」の次に「STAFF」という項目がありますが・・これは、振り付けのスタッフのことなんでしょうか・・・どちらにしても、「制作、オフィス」で4名が記載されています。
銀鉄では、一度キャストとして出演したひとが、その後、舞台には立てないけれど、制作を手伝う。というパターンはあるようです。ただ、団体の所属でもなく、子弟関係、門下生などのグループでもない個人が、このように個別に制作として名前を載せるだけの働きをして、舞台公演が行われているというのも、二期会さんと同じく、20年以上の『継続力』の賜物だと思います。
もちろん、二期会さんの「制作部」にあたる部分でも多くの方が動いているとは思いますが、スタッフ一覧に名前が出るということは、うまくいくと評価を個人として得ますが、反対に何かよくないことがあると、その責任も問われるということです。
ですので、わたしは、関わっている人はすべて名前をクレジットし、その役割を明記した方がいい。そんなことを考えます。
その意味で、今回の銀鉄の公演で残念だったことは二つ。
ひとつは、アンコール進行のまずさ。
私が見に行ったのが初日である20日だったせいもあるかも知れませんが、舞台が終わり、一度、アンコールの拍手の中でキャストが登場し、また、SWJOが出て来てなど進行して・・・・その次、客電が明るくなるわけでもなく、なんだか「抜けた間」があり、アンコールの拍手を続けてもなんの反応もなく、客席でも、ナニナニ?てな雰囲気が漂い始め。で、半分くらいの観客がまだアンコールの拍手を続けているようなタイミングで客電が明るくなり、終了の場内アナウンスが・・・
これは、いかん。ですよね。舞台監督のもっとも大きな仕事のうちのひとつが、アンコールの段取り。出演者の順番を守り、照明と音響さんにキューを出す。アナウンスにも最後にキューを出す。これ、ほんと、大切です。残念なラストでした。
わたしも数多くの舞台監督とかの仕事の中で、アンコールをビシッ!と決められたのは少ないかも知れません。アンコールにもリハーサルと位置決めとかきっかけ決めは必要なのですが、限られた舞台を使ってのリハーサル時間の中で、ついつい、とばしてしまうことも多いかと思いますが・・。
もうひとつは、振り付けの違和感。
私が思うJAZZのビート、アフタービートとシンコペーションで形成されるリズムに乗ってのダンス、身の振り方、振り付け・・・今回の舞台のダンスシーンすべてに感じたのは「JAZZのリズムに乗っていない?」という違和感でした。とくに、メインの曲か何かで、全員でセンターでポーズを決めるリズムのポジションが・・。へんな感じに。
全員が、パッとビシッとポーズを決めるのが最後の小節のリズムの頭で決め、ストップモーションになって。決まりポーズになった次のリズムで、ドラムやサウンドが一斉にビシッとアフタービートを打つ。
このビートを打つ静かな流しているタイミングでストップモーションになり、止まったあと、一拍おいて、バンドのビートがジャン!と打たれる・・・・ものすごく違和感を覚えました。
キャストのダンスの力量などとは関係なく、振り付けそのもののつくり方のような気がしました。
これは、私が解釈しているビートの取り方が違っているのかも知れませんが・・・・・ジャズ系の4ビートで美しくステップを繰り広げるフレッドアステアやジーンケリーのミュージカル映画をむさぼるように見ていたわたし独自の感覚でしかないかも知れませんが・・・・「JAZZの振り付けではないなぁ」と、素朴に思いました。
***************
最後に・・・・・
やっと最後のコメントです。
長く続けて来た、ふたつの舞台公演を比較してブログを読まれた皆様が、それぞれの立場でどのようなことをお感じになったのか、書く方としてはとても不安でオソロシイことではありますが・・・・舞台作品を見たひとりの観客の感想としてとらえていただければと思います。
そして、一番最初に書きましたが、わたしは舞台が好きです。大好きなんです。
落語でも新喜劇でも歌舞伎でもロックコンサートでも芝居でもミュージカルでも発表会でもオペラでもコンサートでも、舞台を使った表現行為が、大好きなんです。
一方で、経済環境が厳しくなる中で、舞台関係の仕事を自分の人生の仕事する方がどんどんと減って行き、地方で、地元のスタッフだけで良質の舞台作品を生み出すことが、スタッフ部門としてかなり厳しい現状であることも知っています。
舞台をつくる側のひと、出演する側の方々、表現を行おうとするひとたちは、その時代時代に応じて、とても刺激的であったりクリエイティブであったりな方が排出し、減ることはありません。
ただ、つくり手側も、舞台として必要な構成要素を体験し、勉強し、知る機会があまりにも少ないので、音楽なら音楽だけ、芝居だったら芝居だけに集中し熱中する方とその周囲の方だけだと、舞台公演というものはその魅力を充分に発揮できません。
記録し編集する総合芸術としての映画・映像作品と対照的な、「一時性」「一瞬性」だけの総合芸術である舞台作品。総合芸術としてはスタッフ部門とのマッチング、充実は、作品力向上のためにはきっても切り離せない要素です。
地元で適切な予算で舞台まわりのことを専門性を持って対応できる企業、スタッフの少なさが、制作サイドの手間と労力を必要とさせ体力的・金銭的な負担をかけていることが現状ではあります。
最後の最後に・・
以前のブログにも書きましたが、「先生方が揃う大人の集まりとしての稽古の仕方、進め方」を行い、古典作品を歌い演奏し演じるという二期会さんと、ひとりの強烈な作・演出・演技指導を行う指導者のもと、それぞれの身の丈にあったオリジナルの台詞ができあがってくる銀河鉄道さん。
今回、観客のひとりとして素朴に思ったたとえとしては・・・・
とても乱暴な言い方ですが・・
たとえば・・・・難易度100の作品が60%できている舞台と、難易度80の作品が85%できている舞台と、どちらが見ていてすーっと素朴に感情移入できるか。生の舞台作品として楽しめるか。生の人間が演じるその物語りからインプレッションを受けるか・・・・・そんなことを考えてしまいました。
オペラとミュージカルを並べて比べる、ということ自体、学問的?芸術分野的には、まったく意味のないことだと思います。
ただ、生活文化として、地方都市に暮らすひとびととが、芸術を学び修練をし、その成果を舞台という場で人前に有料で披露するという行為としては、わたしには“ある同じくくり”に見えました。
長々と書き記して来ましたが、舞台のことを職業にしたくて舞台のアルバイトからスタートし音響、照明、イベント会社に身を置き、仕事として演出台本を書き舞台監督もし、10数年目でその表現をインターネット分野で花を開かせようと進んで、今、マーケティングの世界を生業としている者として、最近は若干客観的に見ることができるようになり、「芸術的表現」を「ひとに伝える手法」としての「舞台」ということについて、思うことを書かせていただきました。
今回初めて出演されたみなさん、何度も出演しているベテランの方、みなさんのこと、実は、羨ましい。
実のところ、毎日の暮らしの中で時間をつくり、稽古をし、舞台に乗る。そんなことを実行している皆さんは、み~んな素敵です。羨ましい。
20数年間、活動を継続されている二期会さんと銀河鉄道さんに改めて敬意を表し、次の作品から、毎回見続けようかなぁと思っています。
あ、でも、このような文章を書くのは、今回だけにしておきます。笑。
あまりにも、たいへん・・時間がかかり過ぎますので・・笑。
たとえば、今回の項目でも、3日間にわたり、合計でどうみても7時間はかけてます・・・苦笑。
ご精読、ありがとうございました。
ご批判、思い違い、事実認識違い、など忌憚なくコメントいただければ幸いです。
あ、でも、無理に、無理して書き込まなくても・・・結構ですので過分なお気遣いはなく・・・。
rookie 机下
※ちなみに、25年以上もいわゆる「裏方、仕掛ける」立場、プランナー、プロデューサーを仕事にして来ましたが、このブログの他の記事にあるように、ギターの弾き語りで人前に立つことを昨年、始めました。
自分の仕事である、企画をしたり、デザイナーやコピーライターやIT技術者というクリエーターを束ねて、その総合として作品をつくって来た自分の行動が、どうも、直接自分の表現を人前にさらしているそのデザイナーやコピーライターなどのクリエーターの連中よりも、「どうも、クリエイティブでないなぁ」と思うようになり・・
表現をするひとたちに対するコンプレックスもあり・・・
昨年、50才になって『何かが起こり・笑』・・・
32年振りにギターを再び手にとり、人前で自分の生身で表現をするようになりました。
クラシックの譜面も読めませんし、長いセリフを覚えて演じることはできませんが、自分なりに、自分の場所で、できることから表現をして行きたいなぁと、二期会さんや銀鉄さんの公演に出ている演奏者、役者のみなさんと同じように、自分そのものをさらけ出して、見に来ている方の前にさらけ出して、その評価や感想を聞きたいと知りたいと・・・・
そんなことを、50を越えてやっております。
いよいよ、最後のブログになりました。
「舞台監督・舞台進行・制作体制」
もっとも複雑で、その団体ごとの個別の事情が現れ、なかなか正論だけでは解決しない問題がたくさんある項目です。
ただ、それは以前のブログにも書きましたが、東京などで行われている、プロ出演者とプロスタッフによる舞台公演にしても、より大きな予算が動き、スポンサーもあり、収益とかより大きな名声・プライドなどが複雑に絡まりあっています。
なので、地方だから、みんなそれぞれ別の職業を持っているから・・などの要素は、多かれ少なかれ、世界中のどんな「ケース」でも持っている要素です。
それぞれの「事情」はあるにせよ、出演者がアマチュアでも職業演奏家でも、公演そのものを職業としている人にせよ団体にせよ、舞台にかけられた作品は、その背景事情を加味することなく、気にすることなく、舞台作品としての評価、批評はあるべきである。そう思っています。
では、 ■■舞台監督・舞台進行・制作体制■■ です。
まずは、舞台監督ですが、舞台監督という職域は、舞台の分野によってその仕事はかなりの専門性を要求されます。
コンサート関係では、英語での呼び方としての「ステージマネージャー」と呼ばれています。
なので、パンフレットのスタッフ一覧を見ると、二期会さんも銀鉄さんも、さすがにこの部分はプロに任せています。
わたしは、すべての舞台行事に「舞台監督」「ステマネ」は配置されるべきポジションだと思っています。
最低限、この職域に「人件費」という予算立てをしない舞台はよくない、と思っています。
予算立てをしないまでも、その職域が持つ役割を持った明確な人物を立てる、ということが、観客に不要なストレスや違和感、「田舎っぽい」とか「なんか、段取りが悪いなぁ」とかの感覚を与えることを防ぎます。
『そんなにかしこまらなくても、大上段に言わなくても、少し段取りが悪くても、それが手作り感があるし、団体の雰囲気も伝わるから、それでいいんですよ』という話は、よく聞きます。
わたしは、それは認めません。舞台の神様に失礼です。そう考えています。
舞台というのは「板の上」と呼ばれ、舞台袖から本舞台に入る前には一礼をし、リハや場当たりが終わって舞台を降りるときには、また舞台に向かって一礼をする。
ひとの立ち居振る舞い、所作が綺麗でかっこよかったり、ぴったりしていることを、「イタに付いてるなぁ」と言いますが、これは、舞台の上で足がしっかりと舞台の板について、重心が座っており見た目に安定感があり美しい姿の語源から来ていると言われています。
こういった文化は、日本舞踊など日本の古典舞台の世界ではまだ生きています。
若いころに日本舞踊の現場に行く時には、ほんとうに身が引き締まって、継続され伝承されて来た日本の「文化に触れている」という感覚を持ったものです。
そういう認識を持っている者として、舞台監督にちゃんと予算を置き、パンフレットにも名前を記載する。このふたつの団体は、きちんと舞台を作り続けている老舗ならではの体制だと思いました。
二期会
二期会さんの舞台監督は福山の方で(20年前、一緒に仕事をさせていただいたときにはそうでした)、もうずいぶん大ベテランの方です。西日本において貴重な存在の方です。この分野で後継者は育っていられるんでしょうか・・。今回のパンフレットには「舞台監督助手」というクレジットで3名の方の名前が記載されています。このうちひとりでも、舞台監督の方の事務所の若い方であれば、舞台業界にとって明るいことです。
また、二期会さんのパンフには、「大道具製作・操作」という項目があり、高松の舞台会社の名前がクレジットされています。小道具として、舞台監督さんの事務所名がクレジットされています。オペラの舞台監督は、オペラの知識が必要です。本人の勉強も必要です。高松では、オペラの舞台監督ができる方は、わたしの知る限りいません。
ですから、パンフレットからだけ判断すると、この二期会さんの体制はさすが20数年の積み重ねで、質と手間と予算のバランスを磨いてきたものなんだなぁと思わせるものです。
オペラの知識が必要な舞台監督のポジションは、西日本で活躍されるベテランを。舞台セットの製作は、十年くらい前でしょうか、高松の音響・舞台製作会社から独立した若手が始めた舞台の会社に発注。小道具は、バレエやオペラを数多く長年手がけている舞台監督の事務所から調達。また、衣裳の主だったものは日本最大の東京衣装から入手し、地元の服装学院さんの協力を得ている。いいバランスですね。
もちろん、このスタッフ一覧の最後にクレジットされている「制作 四国二期会制作部」という項目の持つ大きな意味もあります。練習会場の予約から、出演者への連絡、楽譜のやりとり、衣裳のやりとり、オーケストラへの連絡、依頼しているプロの方々との連絡・・・プロに依頼できない部分の手作業・・・・今回出演されていない会員、先生方の手伝い・・・そして、もっとも大切な協賛依頼とチケット販売・・・・それらの細かな作業と配慮がなくては、最終的に幕は上がりません。
これらのことはパンフレットから想像できますが、その上で、ひとつだけ気になることを・・。
最初の頃に触れましたが、天国の場面でのひとりひとりの動きの中で、あまりにも素人の突っ立ちや意味のない手振りなどが目立った点です。「声が聞こえない」という訓練の必要なことではなく、この舞台上の「立ち居振る舞い」の部分は、舞台監督を含めた制作サイドの配慮、取組みで防げたのではないか、ということが、とても気になりました。
誰かがどこかで、「これで・・仕方ない・・・・」とあきらめたのではないか。「未必の故意」という用語が、よく犯罪もののドラマで使われていますが、リハーサルとか、前日のゲネプロなどでも見えていたはずなのに?と思ってしまいました。
これは、誰かのせい、という犯人さがしの話をしているのではなくて、これだけの人数が動く舞台をつくりあげる体制として、「演出助手」というポジションが必要だったのではないかと。稽古場では、どなたかがその役割をやっていたのかも知れませんが、明確に必要なポジションとして置くべきではなかったのか、と。そんなことを見ている途中から強く思いました。
もしかすると、「舞台監督助手」にある3人の方のどなたかが、その役割を担っていたのかも知れませんが・・。
また、スタッフ一覧には、練習時にピアノを弾くみなさんの名前が5人クレジットされていて、みなさんが集まり生演奏付きで練習することの大変さが窺い知れる記載ですね。
銀河鉄道
銀河鉄道さんのスタッフ一覧を、二期会さんの項目と比較してみると、「制作」で2名、「制作管理」で1名、「オフィス」で1名とクレジットされています。また、「振り付け助手」の次に「STAFF」という項目がありますが・・これは、振り付けのスタッフのことなんでしょうか・・・どちらにしても、「制作、オフィス」で4名が記載されています。
銀鉄では、一度キャストとして出演したひとが、その後、舞台には立てないけれど、制作を手伝う。というパターンはあるようです。ただ、団体の所属でもなく、子弟関係、門下生などのグループでもない個人が、このように個別に制作として名前を載せるだけの働きをして、舞台公演が行われているというのも、二期会さんと同じく、20年以上の『継続力』の賜物だと思います。
もちろん、二期会さんの「制作部」にあたる部分でも多くの方が動いているとは思いますが、スタッフ一覧に名前が出るということは、うまくいくと評価を個人として得ますが、反対に何かよくないことがあると、その責任も問われるということです。
ですので、わたしは、関わっている人はすべて名前をクレジットし、その役割を明記した方がいい。そんなことを考えます。
その意味で、今回の銀鉄の公演で残念だったことは二つ。
ひとつは、アンコール進行のまずさ。
私が見に行ったのが初日である20日だったせいもあるかも知れませんが、舞台が終わり、一度、アンコールの拍手の中でキャストが登場し、また、SWJOが出て来てなど進行して・・・・その次、客電が明るくなるわけでもなく、なんだか「抜けた間」があり、アンコールの拍手を続けてもなんの反応もなく、客席でも、ナニナニ?てな雰囲気が漂い始め。で、半分くらいの観客がまだアンコールの拍手を続けているようなタイミングで客電が明るくなり、終了の場内アナウンスが・・・
これは、いかん。ですよね。舞台監督のもっとも大きな仕事のうちのひとつが、アンコールの段取り。出演者の順番を守り、照明と音響さんにキューを出す。アナウンスにも最後にキューを出す。これ、ほんと、大切です。残念なラストでした。
わたしも数多くの舞台監督とかの仕事の中で、アンコールをビシッ!と決められたのは少ないかも知れません。アンコールにもリハーサルと位置決めとかきっかけ決めは必要なのですが、限られた舞台を使ってのリハーサル時間の中で、ついつい、とばしてしまうことも多いかと思いますが・・。
もうひとつは、振り付けの違和感。
私が思うJAZZのビート、アフタービートとシンコペーションで形成されるリズムに乗ってのダンス、身の振り方、振り付け・・・今回の舞台のダンスシーンすべてに感じたのは「JAZZのリズムに乗っていない?」という違和感でした。とくに、メインの曲か何かで、全員でセンターでポーズを決めるリズムのポジションが・・。へんな感じに。
全員が、パッとビシッとポーズを決めるのが最後の小節のリズムの頭で決め、ストップモーションになって。決まりポーズになった次のリズムで、ドラムやサウンドが一斉にビシッとアフタービートを打つ。
このビートを打つ静かな流しているタイミングでストップモーションになり、止まったあと、一拍おいて、バンドのビートがジャン!と打たれる・・・・ものすごく違和感を覚えました。
キャストのダンスの力量などとは関係なく、振り付けそのもののつくり方のような気がしました。
これは、私が解釈しているビートの取り方が違っているのかも知れませんが・・・・・ジャズ系の4ビートで美しくステップを繰り広げるフレッドアステアやジーンケリーのミュージカル映画をむさぼるように見ていたわたし独自の感覚でしかないかも知れませんが・・・・「JAZZの振り付けではないなぁ」と、素朴に思いました。
***************
最後に・・・・・
やっと最後のコメントです。
長く続けて来た、ふたつの舞台公演を比較してブログを読まれた皆様が、それぞれの立場でどのようなことをお感じになったのか、書く方としてはとても不安でオソロシイことではありますが・・・・舞台作品を見たひとりの観客の感想としてとらえていただければと思います。
そして、一番最初に書きましたが、わたしは舞台が好きです。大好きなんです。
落語でも新喜劇でも歌舞伎でもロックコンサートでも芝居でもミュージカルでも発表会でもオペラでもコンサートでも、舞台を使った表現行為が、大好きなんです。
一方で、経済環境が厳しくなる中で、舞台関係の仕事を自分の人生の仕事する方がどんどんと減って行き、地方で、地元のスタッフだけで良質の舞台作品を生み出すことが、スタッフ部門としてかなり厳しい現状であることも知っています。
舞台をつくる側のひと、出演する側の方々、表現を行おうとするひとたちは、その時代時代に応じて、とても刺激的であったりクリエイティブであったりな方が排出し、減ることはありません。
ただ、つくり手側も、舞台として必要な構成要素を体験し、勉強し、知る機会があまりにも少ないので、音楽なら音楽だけ、芝居だったら芝居だけに集中し熱中する方とその周囲の方だけだと、舞台公演というものはその魅力を充分に発揮できません。
記録し編集する総合芸術としての映画・映像作品と対照的な、「一時性」「一瞬性」だけの総合芸術である舞台作品。総合芸術としてはスタッフ部門とのマッチング、充実は、作品力向上のためにはきっても切り離せない要素です。
地元で適切な予算で舞台まわりのことを専門性を持って対応できる企業、スタッフの少なさが、制作サイドの手間と労力を必要とさせ体力的・金銭的な負担をかけていることが現状ではあります。
最後の最後に・・
以前のブログにも書きましたが、「先生方が揃う大人の集まりとしての稽古の仕方、進め方」を行い、古典作品を歌い演奏し演じるという二期会さんと、ひとりの強烈な作・演出・演技指導を行う指導者のもと、それぞれの身の丈にあったオリジナルの台詞ができあがってくる銀河鉄道さん。
今回、観客のひとりとして素朴に思ったたとえとしては・・・・
とても乱暴な言い方ですが・・
たとえば・・・・難易度100の作品が60%できている舞台と、難易度80の作品が85%できている舞台と、どちらが見ていてすーっと素朴に感情移入できるか。生の舞台作品として楽しめるか。生の人間が演じるその物語りからインプレッションを受けるか・・・・・そんなことを考えてしまいました。
オペラとミュージカルを並べて比べる、ということ自体、学問的?芸術分野的には、まったく意味のないことだと思います。
ただ、生活文化として、地方都市に暮らすひとびととが、芸術を学び修練をし、その成果を舞台という場で人前に有料で披露するという行為としては、わたしには“ある同じくくり”に見えました。
長々と書き記して来ましたが、舞台のことを職業にしたくて舞台のアルバイトからスタートし音響、照明、イベント会社に身を置き、仕事として演出台本を書き舞台監督もし、10数年目でその表現をインターネット分野で花を開かせようと進んで、今、マーケティングの世界を生業としている者として、最近は若干客観的に見ることができるようになり、「芸術的表現」を「ひとに伝える手法」としての「舞台」ということについて、思うことを書かせていただきました。
今回初めて出演されたみなさん、何度も出演しているベテランの方、みなさんのこと、実は、羨ましい。
実のところ、毎日の暮らしの中で時間をつくり、稽古をし、舞台に乗る。そんなことを実行している皆さんは、み~んな素敵です。羨ましい。
20数年間、活動を継続されている二期会さんと銀河鉄道さんに改めて敬意を表し、次の作品から、毎回見続けようかなぁと思っています。
あ、でも、このような文章を書くのは、今回だけにしておきます。笑。
あまりにも、たいへん・・時間がかかり過ぎますので・・笑。
たとえば、今回の項目でも、3日間にわたり、合計でどうみても7時間はかけてます・・・苦笑。
ご精読、ありがとうございました。
ご批判、思い違い、事実認識違い、など忌憚なくコメントいただければ幸いです。
あ、でも、無理に、無理して書き込まなくても・・・結構ですので過分なお気遣いはなく・・・。
rookie 机下
※ちなみに、25年以上もいわゆる「裏方、仕掛ける」立場、プランナー、プロデューサーを仕事にして来ましたが、このブログの他の記事にあるように、ギターの弾き語りで人前に立つことを昨年、始めました。
自分の仕事である、企画をしたり、デザイナーやコピーライターやIT技術者というクリエーターを束ねて、その総合として作品をつくって来た自分の行動が、どうも、直接自分の表現を人前にさらしているそのデザイナーやコピーライターなどのクリエーターの連中よりも、「どうも、クリエイティブでないなぁ」と思うようになり・・
表現をするひとたちに対するコンプレックスもあり・・・
昨年、50才になって『何かが起こり・笑』・・・
32年振りにギターを再び手にとり、人前で自分の生身で表現をするようになりました。
クラシックの譜面も読めませんし、長いセリフを覚えて演じることはできませんが、自分なりに、自分の場所で、できることから表現をして行きたいなぁと、二期会さんや銀鉄さんの公演に出ている演奏者、役者のみなさんと同じように、自分そのものをさらけ出して、見に来ている方の前にさらけ出して、その評価や感想を聞きたいと知りたいと・・・・
そんなことを、50を越えてやっております。
Posted by rookie1957@ストリート at 13:18│Comments(6)
│音楽・舞台・映画
この記事へのコメント
お疲れさまでした。
あまり積極的に演劇系の舞台芸術を見に行く方ではないのですが、
オペラとミュージカルの違い、
出る人と支える人との違いと関わり、
各者の役割、
そして、
自分が見ていてよく感じていた違和感
〜例えば、アンコールのだらだら感 など
とても良くわかりました。
もう少し、舞台を見に行ってみます。
ありがとうございました。
あまり積極的に演劇系の舞台芸術を見に行く方ではないのですが、
オペラとミュージカルの違い、
出る人と支える人との違いと関わり、
各者の役割、
そして、
自分が見ていてよく感じていた違和感
〜例えば、アンコールのだらだら感 など
とても良くわかりました。
もう少し、舞台を見に行ってみます。
ありがとうございました。
Posted by かわい at 2008年10月26日 15:11
★かわい師匠!
コメント、ありがとうございます。
「自分が見ていてよく感じていた違和感」という表現がありましたが、
わたしが感じたことは特別なものではなく、
理屈っぽく言えるかどうかの違いで、同じような「何か」を素朴に感じた方はある程度いたのではないか、と、そんなふうに思います。
わかいさん達のインストゥルメンツのアドリブセッションに、いつかどっぷりと参加できるように、指運とスケールの練習と勉強、がんばりますです。
コメント、ありがとうございます。
「自分が見ていてよく感じていた違和感」という表現がありましたが、
わたしが感じたことは特別なものではなく、
理屈っぽく言えるかどうかの違いで、同じような「何か」を素朴に感じた方はある程度いたのではないか、と、そんなふうに思います。
わかいさん達のインストゥルメンツのアドリブセッションに、いつかどっぷりと参加できるように、指運とスケールの練習と勉強、がんばりますです。
Posted by rookie@いつもの会社での日曜日締切り前・・ at 2008年10月26日 18:21
最後まで読んだなり!!
すごい!
深い!
本当に舞台がお好きなんですね!!
すごい!
深い!
本当に舞台がお好きなんですね!!
Posted by くりす♪ at 2008年10月27日 20:22
★クリス25才姫
ご精読ありがとうございました。
ここまで何人の方が辿り着くのでしょうか・・(笑)
なんだか、書き終えてホッと肩の荷が降りた感じ。っす。
ご精読ありがとうございました。
ここまで何人の方が辿り着くのでしょうか・・(笑)
なんだか、書き終えてホッと肩の荷が降りた感じ。っす。
Posted by rookie☆ラ・フォンティーヌ下見中 at 2008年10月27日 21:23
途中で挫折することもなく、よくできました(笑)
いや、よんだ人たちのほうが偉いかも。うひ
いやいや、rookieがいかに舞台が好きであるか 何を願っているか よくわかりました。
(^-^)/
段取りは大事
板にたったら もう言い訳たたない
常に胸に置いて、今後も精進せねばと思いました。
いや、よんだ人たちのほうが偉いかも。うひ
いやいや、rookieがいかに舞台が好きであるか 何を願っているか よくわかりました。
(^-^)/
段取りは大事
板にたったら もう言い訳たたない
常に胸に置いて、今後も精進せねばと思いました。
Posted by るいまま at 2008年10月27日 23:06
★るいままへ
ご精読ありがとう。
やっぱり「潔さ」に憧れてるんだろうな、と。
自分で書きながら、自分の考えが足りないところ、知識があやふやなところがよく解りました。
もう、寝ます(笑)
ご精読ありがとう。
やっぱり「潔さ」に憧れてるんだろうな、と。
自分で書きながら、自分の考えが足りないところ、知識があやふやなところがよく解りました。
もう、寝ます(笑)
Posted by rookie☆もう寝ます at 2008年10月28日 01:17