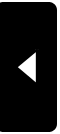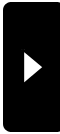2008年10月19日
Vol,6 二期会と銀鉄、公演見ました
二期会のオペラ公演と銀河鉄道のミュージカル公演を、比較して述べています。
もう6回目になります。「番外」を入れると7つ目のブログになります。
残りの項目は次のふたつでしたが・・・
「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」
「制作体制・舞台監督・舞台進行」
前回、Vol,5で、「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」の項目が、「照明」のついて書いただけで長くなったので、パート1として、今回は、「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」のパート2、「音響と舞台セット」となります。
■■舞台効果・・音響、照明、舞台セット■■パート2「音響」 です。
二期会
「音響」の項目については、これは電気的な増幅「PA(パブリックアドレス)」のことになるので、二期会さんの公演には今回は関係がない項目ですね。
東京などのオペラ公演では、ホールや舞台セットの関係でほんの時折、高度な集音マイクを使い、うっすらと舞台セットの中のスピーカーから流す、などの手法がとられることがあると聞いています。(業界仲間の伝聞です。間違っていたら申し訳ありません)
今回の二期会さんの公演時、舞台の最前列、通称「かまち」と呼ばれる舞台の「ふち」にあたる部分に、PZMタイプの床置き集音マイクが等間隔に5,6台置かれていたように見えましたが、これは記録映像の音源取りなんだろうなぁと、ぼんやり見ていました。
銀河鉄道
ちゃんとした発声訓練を受けていない役者の多い(もちろん、「地声」でよく声が出ているひとは多いですが・・)劇団の音響をするというのは、音響会社、音響オペレーターにとっては、これは、かなり困難な仕事です。
基本的に、電気的にいくらでも増幅できますが、『出ていない声は、マイクで拾えません。従って増幅できません。』
その上、銀鉄は「ミュージカル」です。「歌いながら踊る」シーンも多くあります。
今回、久し振りに銀鉄の公演を見ましたが、そのような状況・環境の中で、音響さん、完璧なマイクオペレーションとミキシング操作でした。
オリーブホールやサンポートの小ホールと違い、800人のホールでしたから、完璧にすべての役者の声を最前の方法で拾い、また、その拾った「音としての声」を適格なイコライジングでPAしていました。
イコライジング・・・イコライザーによって、こまかな周波数である音階・音域を、周波数ごとに電気的に上げ下げし、今回の舞台セット、ホール、音楽とのバランスでより自然に、いい音に、調整する技術。とくに、「ハウリング」と呼ばれる、一定の音の自然増幅による「キーーーン」とが「ぶぉーーん」とかいうノイズの発生を排除する中で、いい音をつくること。
その技術力に脱帽です。これは、長い年月、チーフオペレーターのT村さんが、ブツブツと文句を言いながら、リハーサルでは、たぶん、きっと、一度や二度は役者をどなりながら銀鉄との付き合い方を創造し会得し、つくりあげた生の舞台の技術力だと感服しています。
そして、技術だけではなく、マイクそのものや周辺機器など、機材への設備投資も行ってきた成果でもあるのではないかと。
いい機材を使えれば、もっとオペレートは楽になる。でも、高額な機材を地方都市の音響会社で購入し、元を取るまで継続された企業力にも敬意を表します。
今回は面倒な「素人役者」の声のオペレートに加えて、生バンドというもうひとつ大きな負荷が音響マンにかかりました。
役者の声量が出ていないので、役者のマイクをかなりのゲインで高くあげています。と、いうことは、様々な他の音も拾いやすいわけで、生バンドの演奏の音も、役者の声のマイクで拾ってしまう。そんな堂々めぐりの環境の中での音響設計とオペレートだったことは想像できます。
それが、この後に述べる舞台セットとしてのバンド位置であったり、一番最初のブログに書いた、パワードラマーのイノダ先生を透明の遮音パネルで囲うという手段を取ったのだろうな、と思いました。
SWJOの演奏者も、生音が必要以上に出ることに気を使い、フォルテッシモの部分の高まりを抑えたために、全体的にフラットな、JAZZの持ち味である起伏の激しさ、そのコントロールで表現する、という部分が薄まってしまったようにも思えたくらいです。
しかし、役者の声、生演奏の音、素晴らしく「音」がコントロールされた公演だったと思います。
ライフ総合舞台の音響さん、お疲れ様でした。
ただ、この「役者のセリフ、ボーカルの歌詞」がよく聞こえてしまったミュージカル公演を20日の土曜日に見ていたせいで、21日の二期会さんの公演で、「日本語を聞き取るのに、思わず身を乗り出し、耳をそばだててしまった」ことに繋がるのかなぁと。
もちろん、生の声として演奏するオペラと、すべて電気音で構成し成り立っているミュージカルとはもともと違うじゃないか、というご批判もあろうかと思います。
ただ、「どんなジャンルでも、生の舞台を見ることが好きな」私にとって、どんな手法を使ってもいいので、客席に出演者の「パッション」を伝えて欲しい、届けて欲しい、という感覚だけなのです。
続いては・・ ■■舞台効果・・音響、照明、舞台セット■■パート2、その2(笑)「舞台セット」 です。
二期会の舞台美術
照明のパートでも書きましたが、今回の舞台セットは一点もの。二幕、天国のシーンと地獄のシーンと俗界のシーンの変化は、照明効果と中央奥のホリゾント幕をスクリーン変わりに使ったスライド投射の「写真の絵ヅラ」で変化をつけていたわけです。
大きなセットを舞台の中央に置くこと。
大きなセットを中央に置くことで出演者のアクティングエリアが必然的に狭まります。
センター奥はオープンにし、その奥を使った入退場もできる。
舞台上には円形か四角形のアクティングステージがあり、出演者が上がり降りしながら演技できる。
わたしの解釈では、アクティングエリアが狭まれば狭まるほど、
初心者の出演者には効果的である、と思っています。
だだっ広いステージを、ほとんど突っ立つことしかできない出演者を演技指導することほど、
演出家が困惑することはありません。
とくにオペラは、声を出すということ。
声楽の演奏家として音楽を表現するということ。
その上で、演技者として舞台の中で、他の人の楽曲のときやセリフのやりとりをしている間の動きを「演技」として求められています。
これは、かなり、大変なことです。
そこで、今回のこの舞台セットのアイデアは、多くの出演者を助けていたと思います。
とくに天国のシーンは、出演者の衣装がキナリの白一色。ポーズをとってそのポジションに座ったり佇んだりするだけで、ひとつの世界観を表現できるわけで、舞台効果の常とう技ですが、それがきれいに決まる舞台セットとシーン組だったと思います。
ただ・・笑。
来場された方、ほとんどの方が感じていらしただろうと思いますが・・・
ホリゾント幕に映し出される、あの、「現代の高松、さぬきの風景写真」・・・。
なんともいえず、なんとも・・の演出プランです。
想像するに?地元の出演者、制作陣主導で、素材収集と選定がされたのかなぁと。
で、こういった批判とかが出ることは承知の上のプランです。と、回答されるのだろうなぁと。
それは、分かるのではありますが・・・・・・・笑
この舞台美術、舞台効果プランを実行することもできる、「古典にとらわれない、自由な発想を持っている団体なんだ」という意図はわかりますが・・・
その自由度と、舞台上での表現の自由度(あるいは、自由度を表現する演奏力、演技力)の落差が大きいので・・
うーむ。あと、ひとひねり。であったり、写真素材の追求であったり・・。もういっちょ、なにか・・。
という感じでした。
銀河鉄道の舞台美術
今回の設定が昭和30年代。映画の三丁目の夕日の世界ですね。
舞台美術は、アブストラクトされた「かつて高松にあったキャバレー」の店舗内。
こちらも二期会と同じように、1シーンのセットでの舞台公演。
中央に大きな箱がつくられ、その箱の上、2階屋にSWJOのクインテットが乗っかっている。という位置関係でした。
生バンドが入るミュージカルでは、上手・下手の花道や花道の2階屋の部分とか、
今回のように舞台セットの奥の2階部分を使う、というケースがよくあります。
今回のセットとセットにまつわる舞台進行で気になった点。
バンドスペースの2階がとても危険に見えて、気持ちが芝居の中に入ることを妨げる要因のひとつになりました。
柵がない。2階に上がる階段部分にも手すりもない。
近年、舞台上の「安全」は最重要懸案として、舞台業界に重くのしかかっていると思いますが・・・確かに、安全に配慮するとセットなどは「ダサくなる」ことも多く、演出サイドが嫌う「配慮」のうちのひとつです。
途中、ボーカルの方が階段を上がり降りし、ラスト付近では、バンドメンバー全員が、舞台進行中で手を振りながら階段を下りるシーンもあり、足元を気にして階段を上がり降りする「様」が、『役になりきって舞台で演じている演劇』とまったく別の空気が流れ、違和感がありました。
せめて、階段が舞台奥の方に伸びていれば、とも思いました。
昭和30年代をイメージさせる「サマータイム」のシーンでは、この階段がアクティングエリアとして使われて、それなりの効果を出してはいましたが・・・
予算面や、進行上の諸々の条件が重なり、こうなったのだとは思いますが・・。
**************************
さて、音響と舞台セット、舞台美術の項目、無事、校了です。
残すは、最後の最後に、「制作体制・舞台監督・舞台進行」という、公演の根幹に係わる部分について、私が思うことを書きたいと思います。
ご精読、ありがとうございます。
<ブログの記事ごと閲覧ページ数>
10月13日の数字⇒19日の数字を記載しておきます。
Vol.5・・34・・・70
番外 ・・66・・・72
Vol,4・・169・・・187
Vol,3 ・・141・・・151
Vol,2 ・・139・・・144
Vol,1 ・・168・・・186
もう6回目になります。「番外」を入れると7つ目のブログになります。
残りの項目は次のふたつでしたが・・・
「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」
「制作体制・舞台監督・舞台進行」
前回、Vol,5で、「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」の項目が、「照明」のついて書いただけで長くなったので、パート1として、今回は、「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」のパート2、「音響と舞台セット」となります。
■■舞台効果・・音響、照明、舞台セット■■パート2「音響」 です。
二期会
「音響」の項目については、これは電気的な増幅「PA(パブリックアドレス)」のことになるので、二期会さんの公演には今回は関係がない項目ですね。
東京などのオペラ公演では、ホールや舞台セットの関係でほんの時折、高度な集音マイクを使い、うっすらと舞台セットの中のスピーカーから流す、などの手法がとられることがあると聞いています。(業界仲間の伝聞です。間違っていたら申し訳ありません)
今回の二期会さんの公演時、舞台の最前列、通称「かまち」と呼ばれる舞台の「ふち」にあたる部分に、PZMタイプの床置き集音マイクが等間隔に5,6台置かれていたように見えましたが、これは記録映像の音源取りなんだろうなぁと、ぼんやり見ていました。
銀河鉄道
ちゃんとした発声訓練を受けていない役者の多い(もちろん、「地声」でよく声が出ているひとは多いですが・・)劇団の音響をするというのは、音響会社、音響オペレーターにとっては、これは、かなり困難な仕事です。
基本的に、電気的にいくらでも増幅できますが、『出ていない声は、マイクで拾えません。従って増幅できません。』
その上、銀鉄は「ミュージカル」です。「歌いながら踊る」シーンも多くあります。
今回、久し振りに銀鉄の公演を見ましたが、そのような状況・環境の中で、音響さん、完璧なマイクオペレーションとミキシング操作でした。
オリーブホールやサンポートの小ホールと違い、800人のホールでしたから、完璧にすべての役者の声を最前の方法で拾い、また、その拾った「音としての声」を適格なイコライジングでPAしていました。
イコライジング・・・イコライザーによって、こまかな周波数である音階・音域を、周波数ごとに電気的に上げ下げし、今回の舞台セット、ホール、音楽とのバランスでより自然に、いい音に、調整する技術。とくに、「ハウリング」と呼ばれる、一定の音の自然増幅による「キーーーン」とが「ぶぉーーん」とかいうノイズの発生を排除する中で、いい音をつくること。
その技術力に脱帽です。これは、長い年月、チーフオペレーターのT村さんが、ブツブツと文句を言いながら、リハーサルでは、たぶん、きっと、一度や二度は役者をどなりながら銀鉄との付き合い方を創造し会得し、つくりあげた生の舞台の技術力だと感服しています。
そして、技術だけではなく、マイクそのものや周辺機器など、機材への設備投資も行ってきた成果でもあるのではないかと。
いい機材を使えれば、もっとオペレートは楽になる。でも、高額な機材を地方都市の音響会社で購入し、元を取るまで継続された企業力にも敬意を表します。
今回は面倒な「素人役者」の声のオペレートに加えて、生バンドというもうひとつ大きな負荷が音響マンにかかりました。
役者の声量が出ていないので、役者のマイクをかなりのゲインで高くあげています。と、いうことは、様々な他の音も拾いやすいわけで、生バンドの演奏の音も、役者の声のマイクで拾ってしまう。そんな堂々めぐりの環境の中での音響設計とオペレートだったことは想像できます。
それが、この後に述べる舞台セットとしてのバンド位置であったり、一番最初のブログに書いた、パワードラマーのイノダ先生を透明の遮音パネルで囲うという手段を取ったのだろうな、と思いました。
SWJOの演奏者も、生音が必要以上に出ることに気を使い、フォルテッシモの部分の高まりを抑えたために、全体的にフラットな、JAZZの持ち味である起伏の激しさ、そのコントロールで表現する、という部分が薄まってしまったようにも思えたくらいです。
しかし、役者の声、生演奏の音、素晴らしく「音」がコントロールされた公演だったと思います。
ライフ総合舞台の音響さん、お疲れ様でした。
ただ、この「役者のセリフ、ボーカルの歌詞」がよく聞こえてしまったミュージカル公演を20日の土曜日に見ていたせいで、21日の二期会さんの公演で、「日本語を聞き取るのに、思わず身を乗り出し、耳をそばだててしまった」ことに繋がるのかなぁと。
もちろん、生の声として演奏するオペラと、すべて電気音で構成し成り立っているミュージカルとはもともと違うじゃないか、というご批判もあろうかと思います。
ただ、「どんなジャンルでも、生の舞台を見ることが好きな」私にとって、どんな手法を使ってもいいので、客席に出演者の「パッション」を伝えて欲しい、届けて欲しい、という感覚だけなのです。
続いては・・ ■■舞台効果・・音響、照明、舞台セット■■パート2、その2(笑)「舞台セット」 です。
二期会の舞台美術
照明のパートでも書きましたが、今回の舞台セットは一点もの。二幕、天国のシーンと地獄のシーンと俗界のシーンの変化は、照明効果と中央奥のホリゾント幕をスクリーン変わりに使ったスライド投射の「写真の絵ヅラ」で変化をつけていたわけです。
大きなセットを舞台の中央に置くこと。
大きなセットを中央に置くことで出演者のアクティングエリアが必然的に狭まります。
センター奥はオープンにし、その奥を使った入退場もできる。
舞台上には円形か四角形のアクティングステージがあり、出演者が上がり降りしながら演技できる。
わたしの解釈では、アクティングエリアが狭まれば狭まるほど、
初心者の出演者には効果的である、と思っています。
だだっ広いステージを、ほとんど突っ立つことしかできない出演者を演技指導することほど、
演出家が困惑することはありません。
とくにオペラは、声を出すということ。
声楽の演奏家として音楽を表現するということ。
その上で、演技者として舞台の中で、他の人の楽曲のときやセリフのやりとりをしている間の動きを「演技」として求められています。
これは、かなり、大変なことです。
そこで、今回のこの舞台セットのアイデアは、多くの出演者を助けていたと思います。
とくに天国のシーンは、出演者の衣装がキナリの白一色。ポーズをとってそのポジションに座ったり佇んだりするだけで、ひとつの世界観を表現できるわけで、舞台効果の常とう技ですが、それがきれいに決まる舞台セットとシーン組だったと思います。
ただ・・笑。
来場された方、ほとんどの方が感じていらしただろうと思いますが・・・
ホリゾント幕に映し出される、あの、「現代の高松、さぬきの風景写真」・・・。
なんともいえず、なんとも・・の演出プランです。
想像するに?地元の出演者、制作陣主導で、素材収集と選定がされたのかなぁと。
で、こういった批判とかが出ることは承知の上のプランです。と、回答されるのだろうなぁと。
それは、分かるのではありますが・・・・・・・笑
この舞台美術、舞台効果プランを実行することもできる、「古典にとらわれない、自由な発想を持っている団体なんだ」という意図はわかりますが・・・
その自由度と、舞台上での表現の自由度(あるいは、自由度を表現する演奏力、演技力)の落差が大きいので・・
うーむ。あと、ひとひねり。であったり、写真素材の追求であったり・・。もういっちょ、なにか・・。
という感じでした。
銀河鉄道の舞台美術
今回の設定が昭和30年代。映画の三丁目の夕日の世界ですね。
舞台美術は、アブストラクトされた「かつて高松にあったキャバレー」の店舗内。
こちらも二期会と同じように、1シーンのセットでの舞台公演。
中央に大きな箱がつくられ、その箱の上、2階屋にSWJOのクインテットが乗っかっている。という位置関係でした。
生バンドが入るミュージカルでは、上手・下手の花道や花道の2階屋の部分とか、
今回のように舞台セットの奥の2階部分を使う、というケースがよくあります。
今回のセットとセットにまつわる舞台進行で気になった点。
バンドスペースの2階がとても危険に見えて、気持ちが芝居の中に入ることを妨げる要因のひとつになりました。
柵がない。2階に上がる階段部分にも手すりもない。
近年、舞台上の「安全」は最重要懸案として、舞台業界に重くのしかかっていると思いますが・・・確かに、安全に配慮するとセットなどは「ダサくなる」ことも多く、演出サイドが嫌う「配慮」のうちのひとつです。
途中、ボーカルの方が階段を上がり降りし、ラスト付近では、バンドメンバー全員が、舞台進行中で手を振りながら階段を下りるシーンもあり、足元を気にして階段を上がり降りする「様」が、『役になりきって舞台で演じている演劇』とまったく別の空気が流れ、違和感がありました。
せめて、階段が舞台奥の方に伸びていれば、とも思いました。
昭和30年代をイメージさせる「サマータイム」のシーンでは、この階段がアクティングエリアとして使われて、それなりの効果を出してはいましたが・・・
予算面や、進行上の諸々の条件が重なり、こうなったのだとは思いますが・・。
**************************
さて、音響と舞台セット、舞台美術の項目、無事、校了です。
残すは、最後の最後に、「制作体制・舞台監督・舞台進行」という、公演の根幹に係わる部分について、私が思うことを書きたいと思います。
ご精読、ありがとうございます。
<ブログの記事ごと閲覧ページ数>
10月13日の数字⇒19日の数字を記載しておきます。
Vol.5・・34・・・70
番外 ・・66・・・72
Vol,4・・169・・・187
Vol,3 ・・141・・・151
Vol,2 ・・139・・・144
Vol,1 ・・168・・・186
Posted by rookie1957@ストリート at 17:57│Comments(0)
│音楽・舞台・映画