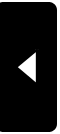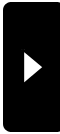2008年09月29日
二期会と銀鉄、公演見ましたVol,2
二期会のオペラ公演と銀河鉄道のミュージカル公演を、比較して述べます。
さて、比較の第2弾です。
前回のブログで予告した比較項目に、これをひとつ追加しました。
■■団体■■
一観客から見た二期会
個人の演奏家や先生方が行う「発表会」「趣味の会」とは一線を画し、プロの演奏家として、きちんとした舞台公演を行う。
演出家、舞台装置、舞台監督、衣裳、道具などそれぞれの業界のプロに依頼。もちろん倹約できるところは倹約をおこなうけれど、演出を中央から招き、演奏家も客演を入れ有料の舞台公演としてオペラを地域にも根付かせようとしている。
後進を育てる意味でも、団体の存続の意からも合唱部分や配役の一部を若手を起用している。
私は、四国二期会の公演を見るとき(数年に1回ですが)外国の歌劇団が行う公演とは違った感覚で観劇しています。
最高級の演奏・演技を愉しむ。というニュアンスより、「地方都市でオペラという総合芸術を公演し続ける団体を応援したい」という気持ちが強いかも知れません。
こう書くと、それは本意ではない。と関係者がおっしゃるかも知れませんね。
オペラは当然既に楽譜があり、百年以上様々な人々が演奏している歴史を持っている。古いVHSテープがあり、CDもあり、DVD映像もある。多くのオペラファンや演奏家はイタリアなどで生の舞台も見て、誰がどんな歌い方をし演技をし演出が為されているかという膨大な情報を持っている。声楽としての難易度の高さに加えて、その上「言語」の壁の厚さがある。様々なハードルがある中で、原語での上演をこだわり続ける芸術。
わたしは、オペラ観劇は、「事前学習マル必舞台芸術」だと認識している。観る前に学習すればするほどより深い味わいや愉しみ、深い感動を味わうことができる芸術だと。
つまり、オペラを愉しむ観客は、筋書きも楽曲も知っている。その自分が知っている楽曲を、「さて、今日の演奏家はどんなに歌うのか、演じるのか。どんな演出が為されているのかなぁ」と、手ぐすねひいて客席に座っているのである。
これは、演じ手には、嫌なものではないですか?
銀河鉄道
以前は「劇団」とすることなく、1回づつの公演で解散。次に芝居をやるときに集まりたい人がまた集まる。ということを繰り返して年月を重ねて行っていた。つまり、「自分の人生にとって1回だけ、日常の生活と離れて夜な夜な練習に没頭して舞台に立ちたい」という強い意志をもった素人が集まっていたと思います。
その「思い」とか「熱」とかを巧みに導く劇団付き作者がいて、演出も行う。以前は、入団して来た素人の役者希望者の性格、声、持ってうまれた雰囲気を見ながら、作品の中で役を与え、その「素人に合った」台本を書くことをやっていた。今はどうなんだろう・・。
次回行う作品構想ができると、役者募集を行う。
役者のトレーニングや基礎練習をやりながら、ひとつのシーンの台本を読ませる。
そのときに集まった役者の顔触れを見ながら、配役を決め、作品の登場人物を練りながら固めてゆく。
練習を重ねながら、役者は、次のシーンの台本を待つ。
銀河鉄道は、毎回その時々の団員に合わせながら、また、新しい「自分」を発見させながら作品をつくりだしてゆく。
今は、稽古が始まる時には台本はすでに出来上がっていることが多いのだろうか・・・
つまり、銀河鉄道は「高校野球球児にとっての甲子園」と同じである。(で、あった?)
このたとえで行くと、二期会の公演活動は、「メジャーリーグ」ではなく、「NPB、日本プロ野球機構が運営するプロ野球」でもないが、「プロの野球」ではある。
音楽の演奏だけで生計を立てている方も居り、学校などでの音楽指導を生業にしている方、音楽を習っている方。そんな方々で二期会は構成されているのに対比して、銀鉄は「プレーを職業としていない高校野球」である。
こう比べると・・・こんなこともある。
プロ野球の試合よりも、1回づつの戦いでトーナメント戦の生き残りをかける、その厳しさに挑む高校生どうしの試合の方が、より強い感動を与えること。こんなこともあるだろう。
■■演出、演出家■■
二期会
今回の舞台を通して、ずっと感じてしまっていたのは・・・「この演出家は、今回の舞台作品の演出を”投げて”いるのか?」ということでした。言い方がキツイかも知れませんが、「演出を職業としたかった」私は、演出には、厳しい目で見ます。
言い方を変えると、出演者の数の多さと練習スケジュールの都合なのか、あとで書きますが、舞台製作上のシステムの問題なのか、『すべての出演者に目の行き届いていない』シーンが目に付いたんです。
とくに「天国」のシーン。絵的にはとても美しく、配慮された人物のポジションだったと思いますが、ひとたび役者が動き、短いセリフを何人かが分けて語るシーンの処理が、あまりにも稚拙でした。
登場人物は、シーンの意味と配役の意味を自分で考えて、動きをつけ、それを稽古場で演出家にぶつけ、指導を受け固めて行く。そんな流れだと思うのですが・・・
もうひとつ気になったことは「出演者に任せている範疇の問題である」としたときに、でも、それが一定レベル以下の場合、演出家はどこまで口を出すのか。これは、世の演出家、それぞれ皆さんの考えがあり、それぞれの演出家のスタイルがありますから、そのスタイルは尊重します。
応援する気持ちで見ますが、でも結果がすべてですから、「締まりのないシーン」を見るのは、辛いですね。
それから、今回、上演中のそこかしこで笑いが起こっていましたが、そのうちのほとんどは、「天国と地獄」の台詞や歌詞の中にあるウィットではなく、古典作品の節々に挟み込んでいた「現代ネタ」で笑いが起きていました。
もちろん、そもそも喜歌劇という分野は、「芝居小屋」的な劇場で、古のひとたちの数少ない娯楽として営まれていたのだから、今に残っている歌詞そのものが、当時としての「現代ネタ」だったのだ。という解釈もよく分かりますが・・。
『演出家がどこまで出演者のアドリブを許し、そのアドリブが渦巻く中でも、どのように演出を貫き通すのか』
この部分が「見えない」「定まっていないように見える」舞台だと感じました。
銀河鉄道
銀鉄は、上村氏の劇団です。氏の作品を見て、あの舞台に立ちたいと集まったひとたちで芝居をしているので、すべてまるごと上村氏の作品です。ですから、あのいつものように描かれる世界観と手法が嫌であれば、見なければいい。これはシンプルな原則です。それは、承知の上で書きます。
二期会で書いたこととは正反対に、銀鉄の芝居を見て思ったのは、『演出家の呪縛から解放された、役者ひとりひとりのほんとうの個性を見たい』ということでした。
そして、演出家としての上村氏の「次の一手」をもっと見たい、と思いました。
具体的に言うと、銀鉄・上村台本の大きな特徴であるピンでの「長ゼリ」を半分にカットして凝縮する。
そのカットで余った「時間」を集めて、今回の展開になかった『次の1シーン』を上村氏に生み出してもらう。
次の1シーンということは、もうひとつの裏ストーリー。もう「ふたつ」でもいいくらい。
氏の「楽しみ」である長ゼリを半分取り上げ、氏が役者を追い込むように、氏を「もうひとつの展開を!」と追い詰めて、それで出てくるシーン、ストーリー、展開に「遭遇」してみたいですね。
主役級の男女が、特攻隊の生き残りとそれをも守っていた現地の女子学生だったという「裏筋」が明らかになったとき、私は、全部の登場人物の「裏ストーリー」がこれからジャンジャカ明らかになり、後半から終盤までの間に、怒涛のようにどんでん返しが続くのかと思いきや・・・・あのふたりだけの裏ストーリー・・・。
上村中毒にかつて侵された者としては、「もっともっと!」ですよねぇ。
こどもや家族に仕送りしているのが、実は、妄想で、子供殺しの逃亡者だった。とか。
おかまチックな支配人が、高松の闇の世界のボスで上海に通じてる大物だったとか。
長ゼリを聞きながら、「先を読んでみよう」という気でいろいろと妄想してましたが・・笑。見事な肩すかし、でした。
二期会については、古典をどう演出し、「地方で頑張る演奏家たちが集まる集団」を、「中央から稽古に参加して指導する」演出家が短時間でどんな腕を見せるか。
銀鉄については、座付き作者・演出家である上村氏にどうやって、「もっともっと」とハッパをかけ、次のシーンを捻出してもらうか。
これからも演出に注目したい。演出を愉しみたい。
************************
さて、本日、日曜日につき、ここまでにしておきます。もう寝ないと。
次回は、次のような項目を比較してみます。の、つもりです・・。
「音楽」
「演奏」
演技・歌「主役級の出演者、役者」
演技・歌「それ以外の出演者」
「制作体制・舞台監督・舞台進行」
「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」
「観客」
「観劇後に退場する観客の雰囲気(勝手な観察)」
「あとがき・・・・」
さて、比較の第2弾です。
前回のブログで予告した比較項目に、これをひとつ追加しました。
■■団体■■
一観客から見た二期会
個人の演奏家や先生方が行う「発表会」「趣味の会」とは一線を画し、プロの演奏家として、きちんとした舞台公演を行う。
演出家、舞台装置、舞台監督、衣裳、道具などそれぞれの業界のプロに依頼。もちろん倹約できるところは倹約をおこなうけれど、演出を中央から招き、演奏家も客演を入れ有料の舞台公演としてオペラを地域にも根付かせようとしている。
後進を育てる意味でも、団体の存続の意からも合唱部分や配役の一部を若手を起用している。
私は、四国二期会の公演を見るとき(数年に1回ですが)外国の歌劇団が行う公演とは違った感覚で観劇しています。
最高級の演奏・演技を愉しむ。というニュアンスより、「地方都市でオペラという総合芸術を公演し続ける団体を応援したい」という気持ちが強いかも知れません。
こう書くと、それは本意ではない。と関係者がおっしゃるかも知れませんね。
オペラは当然既に楽譜があり、百年以上様々な人々が演奏している歴史を持っている。古いVHSテープがあり、CDもあり、DVD映像もある。多くのオペラファンや演奏家はイタリアなどで生の舞台も見て、誰がどんな歌い方をし演技をし演出が為されているかという膨大な情報を持っている。声楽としての難易度の高さに加えて、その上「言語」の壁の厚さがある。様々なハードルがある中で、原語での上演をこだわり続ける芸術。
わたしは、オペラ観劇は、「事前学習マル必舞台芸術」だと認識している。観る前に学習すればするほどより深い味わいや愉しみ、深い感動を味わうことができる芸術だと。
つまり、オペラを愉しむ観客は、筋書きも楽曲も知っている。その自分が知っている楽曲を、「さて、今日の演奏家はどんなに歌うのか、演じるのか。どんな演出が為されているのかなぁ」と、手ぐすねひいて客席に座っているのである。
これは、演じ手には、嫌なものではないですか?
銀河鉄道
以前は「劇団」とすることなく、1回づつの公演で解散。次に芝居をやるときに集まりたい人がまた集まる。ということを繰り返して年月を重ねて行っていた。つまり、「自分の人生にとって1回だけ、日常の生活と離れて夜な夜な練習に没頭して舞台に立ちたい」という強い意志をもった素人が集まっていたと思います。
その「思い」とか「熱」とかを巧みに導く劇団付き作者がいて、演出も行う。以前は、入団して来た素人の役者希望者の性格、声、持ってうまれた雰囲気を見ながら、作品の中で役を与え、その「素人に合った」台本を書くことをやっていた。今はどうなんだろう・・。
次回行う作品構想ができると、役者募集を行う。
役者のトレーニングや基礎練習をやりながら、ひとつのシーンの台本を読ませる。
そのときに集まった役者の顔触れを見ながら、配役を決め、作品の登場人物を練りながら固めてゆく。
練習を重ねながら、役者は、次のシーンの台本を待つ。
銀河鉄道は、毎回その時々の団員に合わせながら、また、新しい「自分」を発見させながら作品をつくりだしてゆく。
今は、稽古が始まる時には台本はすでに出来上がっていることが多いのだろうか・・・
つまり、銀河鉄道は「高校野球球児にとっての甲子園」と同じである。(で、あった?)
このたとえで行くと、二期会の公演活動は、「メジャーリーグ」ではなく、「NPB、日本プロ野球機構が運営するプロ野球」でもないが、「プロの野球」ではある。
音楽の演奏だけで生計を立てている方も居り、学校などでの音楽指導を生業にしている方、音楽を習っている方。そんな方々で二期会は構成されているのに対比して、銀鉄は「プレーを職業としていない高校野球」である。
こう比べると・・・こんなこともある。
プロ野球の試合よりも、1回づつの戦いでトーナメント戦の生き残りをかける、その厳しさに挑む高校生どうしの試合の方が、より強い感動を与えること。こんなこともあるだろう。
■■演出、演出家■■
二期会
今回の舞台を通して、ずっと感じてしまっていたのは・・・「この演出家は、今回の舞台作品の演出を”投げて”いるのか?」ということでした。言い方がキツイかも知れませんが、「演出を職業としたかった」私は、演出には、厳しい目で見ます。
言い方を変えると、出演者の数の多さと練習スケジュールの都合なのか、あとで書きますが、舞台製作上のシステムの問題なのか、『すべての出演者に目の行き届いていない』シーンが目に付いたんです。
とくに「天国」のシーン。絵的にはとても美しく、配慮された人物のポジションだったと思いますが、ひとたび役者が動き、短いセリフを何人かが分けて語るシーンの処理が、あまりにも稚拙でした。
登場人物は、シーンの意味と配役の意味を自分で考えて、動きをつけ、それを稽古場で演出家にぶつけ、指導を受け固めて行く。そんな流れだと思うのですが・・・
もうひとつ気になったことは「出演者に任せている範疇の問題である」としたときに、でも、それが一定レベル以下の場合、演出家はどこまで口を出すのか。これは、世の演出家、それぞれ皆さんの考えがあり、それぞれの演出家のスタイルがありますから、そのスタイルは尊重します。
応援する気持ちで見ますが、でも結果がすべてですから、「締まりのないシーン」を見るのは、辛いですね。
それから、今回、上演中のそこかしこで笑いが起こっていましたが、そのうちのほとんどは、「天国と地獄」の台詞や歌詞の中にあるウィットではなく、古典作品の節々に挟み込んでいた「現代ネタ」で笑いが起きていました。
もちろん、そもそも喜歌劇という分野は、「芝居小屋」的な劇場で、古のひとたちの数少ない娯楽として営まれていたのだから、今に残っている歌詞そのものが、当時としての「現代ネタ」だったのだ。という解釈もよく分かりますが・・。
『演出家がどこまで出演者のアドリブを許し、そのアドリブが渦巻く中でも、どのように演出を貫き通すのか』
この部分が「見えない」「定まっていないように見える」舞台だと感じました。
銀河鉄道
銀鉄は、上村氏の劇団です。氏の作品を見て、あの舞台に立ちたいと集まったひとたちで芝居をしているので、すべてまるごと上村氏の作品です。ですから、あのいつものように描かれる世界観と手法が嫌であれば、見なければいい。これはシンプルな原則です。それは、承知の上で書きます。
二期会で書いたこととは正反対に、銀鉄の芝居を見て思ったのは、『演出家の呪縛から解放された、役者ひとりひとりのほんとうの個性を見たい』ということでした。
そして、演出家としての上村氏の「次の一手」をもっと見たい、と思いました。
具体的に言うと、銀鉄・上村台本の大きな特徴であるピンでの「長ゼリ」を半分にカットして凝縮する。
そのカットで余った「時間」を集めて、今回の展開になかった『次の1シーン』を上村氏に生み出してもらう。
次の1シーンということは、もうひとつの裏ストーリー。もう「ふたつ」でもいいくらい。
氏の「楽しみ」である長ゼリを半分取り上げ、氏が役者を追い込むように、氏を「もうひとつの展開を!」と追い詰めて、それで出てくるシーン、ストーリー、展開に「遭遇」してみたいですね。
主役級の男女が、特攻隊の生き残りとそれをも守っていた現地の女子学生だったという「裏筋」が明らかになったとき、私は、全部の登場人物の「裏ストーリー」がこれからジャンジャカ明らかになり、後半から終盤までの間に、怒涛のようにどんでん返しが続くのかと思いきや・・・・あのふたりだけの裏ストーリー・・・。
上村中毒にかつて侵された者としては、「もっともっと!」ですよねぇ。
こどもや家族に仕送りしているのが、実は、妄想で、子供殺しの逃亡者だった。とか。
おかまチックな支配人が、高松の闇の世界のボスで上海に通じてる大物だったとか。
長ゼリを聞きながら、「先を読んでみよう」という気でいろいろと妄想してましたが・・笑。見事な肩すかし、でした。
二期会については、古典をどう演出し、「地方で頑張る演奏家たちが集まる集団」を、「中央から稽古に参加して指導する」演出家が短時間でどんな腕を見せるか。
銀鉄については、座付き作者・演出家である上村氏にどうやって、「もっともっと」とハッパをかけ、次のシーンを捻出してもらうか。
これからも演出に注目したい。演出を愉しみたい。
************************
さて、本日、日曜日につき、ここまでにしておきます。もう寝ないと。
次回は、次のような項目を比較してみます。の、つもりです・・。
「音楽」
「演奏」
演技・歌「主役級の出演者、役者」
演技・歌「それ以外の出演者」
「制作体制・舞台監督・舞台進行」
「舞台効果・・音響、照明、舞台セット」
「観客」
「観劇後に退場する観客の雰囲気(勝手な観察)」
「あとがき・・・・」
Posted by rookie1957@ストリート at 01:27│Comments(3)
│音楽・舞台・映画
この記事へのコメント
二期会関係者です。
いつもながらの鋭い批評です。
その通りだと感じている部分が多いです。
我々の団体としては、地方都市においてオペラを継続して公演していくことに価値を見いだしています。
これは結構大変なことです。
■演出家について
今回の演出家、僕は好きです。
今までに出会った演出家の中でも優れた人だと思います。
その演出家に答えられなかったのは、こちらサイドのレベルの低さです。
演出家がいつも言っていた「80%の言葉はきちんと客席に届けなさい」
残念ながらできていませんでしたネ。
演奏者として、「言葉」を客席に届ける事、あたりまえであり必要なことです。
■演出手法について
どの演出家も、それぞれ個々のレベルに合わせた助言・指導をします。
今回の演出家は、ある程度できる演奏者には自分で考えることを要求し、基礎ができていない演奏家には徹底的に基礎的部分の指導をしていました。(まるで養成所のように)
稽古において、その部分に時間をさいてしまった。
ただ基礎的な部分は、2~3ヶ月で大きく進化するものではありませんが。
そんな意味で、舞台が整理されておらず場面において差が大きかったと思います。
舞台の隅々まで演出家の意図が通っていなかった。
演出家の責任というより、演奏者サイドの責任が多いですね。
■台詞のアドリブ的な部分について
それは私自身のことで言うと、2ヶ所ですね。
最初の「本日は~」で始まったくだりは、確かに不必要な部分です。
台本にはありません。
本番3週間ぐらい前に、高松のお客さんは感情を外に出さない。笑わない。
なんとかしたい!
お客さんをほぐしたい、と考えてやりました。
一応演出家に了承は取りました。
次の「そんなの関係ない」からのくだり
これは、2ヶ月ぐらい前の稽古から毎回ネタを変えてやってました。
問題は、僕らがネタをやった後の処理だと思うのです。
僕的には、「吉本新喜劇の中で誰かがギャグをやった後に、ストーリーに戻っていく」そんな雰囲気を他の皆さんにやってほしかったんですけど、上手くいってなかったと思います。
稽古中の傑作編
その1
(本番前に衣裳スタッフが、ANAのシステムトラブルでJALに乗り換えて高松に来たため、衣裳合わせが大幅に遅れた)日のネタ。
「そんなの関係ね~」
「お前、それ古いだろ」
ポニョ
「ところでお前、今日飛行機が遅れて遅刻しただろ」
「システムトラブルで、JALに乗って来たんですよ~」
「なに!ギャルに乗って来たのか?」
「下ネタかよー」(ツッコミ)
その2
「そんなの関係ね~」
「そんなの関係ね~」と(プルートも同じ動作)
「プルートよ、お前もかー」
■喜歌劇
今回の演目は「喜歌劇」なわけです。
さて、この「喜歌劇」をどうとらえるか?
「喜歌劇」って何なのか?
これは、日本人にとっては一番演じにくい作品たちだと思います。
シリアスなオペラとは違った作品群なわけです。
ウィーンのフォルクスオーパー(庶民的な歌劇場)でよく演じられていますが、客席とのキャッチボールが多くあり、劇場みんなで楽しんでいます。
そこの所をもっとおしゃれに表現したかったですね。
まだまだ書きたいのですが疲れました。
創作作品は、書き手の思いが強くければ強いほど必要以上に長くなりくどくなる。一般論です。
では、次回を期待しております。
ブログも
Sさんとの交流会は決まり次第連絡します。
「あしたさぬき」上でも、会社のPCでもありませんよ。
Ciao Ciao
いつもながらの鋭い批評です。
その通りだと感じている部分が多いです。
我々の団体としては、地方都市においてオペラを継続して公演していくことに価値を見いだしています。
これは結構大変なことです。
■演出家について
今回の演出家、僕は好きです。
今までに出会った演出家の中でも優れた人だと思います。
その演出家に答えられなかったのは、こちらサイドのレベルの低さです。
演出家がいつも言っていた「80%の言葉はきちんと客席に届けなさい」
残念ながらできていませんでしたネ。
演奏者として、「言葉」を客席に届ける事、あたりまえであり必要なことです。
■演出手法について
どの演出家も、それぞれ個々のレベルに合わせた助言・指導をします。
今回の演出家は、ある程度できる演奏者には自分で考えることを要求し、基礎ができていない演奏家には徹底的に基礎的部分の指導をしていました。(まるで養成所のように)
稽古において、その部分に時間をさいてしまった。
ただ基礎的な部分は、2~3ヶ月で大きく進化するものではありませんが。
そんな意味で、舞台が整理されておらず場面において差が大きかったと思います。
舞台の隅々まで演出家の意図が通っていなかった。
演出家の責任というより、演奏者サイドの責任が多いですね。
■台詞のアドリブ的な部分について
それは私自身のことで言うと、2ヶ所ですね。
最初の「本日は~」で始まったくだりは、確かに不必要な部分です。
台本にはありません。
本番3週間ぐらい前に、高松のお客さんは感情を外に出さない。笑わない。
なんとかしたい!
お客さんをほぐしたい、と考えてやりました。
一応演出家に了承は取りました。
次の「そんなの関係ない」からのくだり
これは、2ヶ月ぐらい前の稽古から毎回ネタを変えてやってました。
問題は、僕らがネタをやった後の処理だと思うのです。
僕的には、「吉本新喜劇の中で誰かがギャグをやった後に、ストーリーに戻っていく」そんな雰囲気を他の皆さんにやってほしかったんですけど、上手くいってなかったと思います。
稽古中の傑作編
その1
(本番前に衣裳スタッフが、ANAのシステムトラブルでJALに乗り換えて高松に来たため、衣裳合わせが大幅に遅れた)日のネタ。
「そんなの関係ね~」
「お前、それ古いだろ」
ポニョ
「ところでお前、今日飛行機が遅れて遅刻しただろ」
「システムトラブルで、JALに乗って来たんですよ~」
「なに!ギャルに乗って来たのか?」
「下ネタかよー」(ツッコミ)
その2
「そんなの関係ね~」
「そんなの関係ね~」と(プルートも同じ動作)
「プルートよ、お前もかー」
■喜歌劇
今回の演目は「喜歌劇」なわけです。
さて、この「喜歌劇」をどうとらえるか?
「喜歌劇」って何なのか?
これは、日本人にとっては一番演じにくい作品たちだと思います。
シリアスなオペラとは違った作品群なわけです。
ウィーンのフォルクスオーパー(庶民的な歌劇場)でよく演じられていますが、客席とのキャッチボールが多くあり、劇場みんなで楽しんでいます。
そこの所をもっとおしゃれに表現したかったですね。
まだまだ書きたいのですが疲れました。
創作作品は、書き手の思いが強くければ強いほど必要以上に長くなりくどくなる。一般論です。
では、次回を期待しております。
ブログも
Sさんとの交流会は決まり次第連絡します。
「あしたさぬき」上でも、会社のPCでもありませんよ。
Ciao Ciao
Posted by セバスティアーノ at 2008年09月29日 03:47
二期会関係者の方、さっそくのコメント、ありがとうございます。
このコメント内容から、これから書こうとしていた懸念や疑問のうち、いくつかの項目がクリアされました。
演出家の方への過度な叱責の表現、失礼しました。
また、稽古中のネタばらし、ありがとうございます。わたしとしては、「下ネタかよ~」のネタをやったときの高松の観客の反応を見てみたかったですね。
しかし・・・こ、「こ、交流会」の話題をここで書くとは・・・・。
うーむ、袖の下をちらつかされたみたいで、次回からの比較ブログの辛口部分の筆が鈍るかも・・・
このコメント内容から、これから書こうとしていた懸念や疑問のうち、いくつかの項目がクリアされました。
演出家の方への過度な叱責の表現、失礼しました。
また、稽古中のネタばらし、ありがとうございます。わたしとしては、「下ネタかよ~」のネタをやったときの高松の観客の反応を見てみたかったですね。
しかし・・・こ、「こ、交流会」の話題をここで書くとは・・・・。
うーむ、袖の下をちらつかされたみたいで、次回からの比較ブログの辛口部分の筆が鈍るかも・・・
Posted by rookie at 2008年09月29日 06:43
rookie 様
いいえ、その通り、鋭いです。
今回の舞台!僕が客席から観ていたら、rookie様のように感じていたと思います。
僕自身も稽古中に『このままでいいの?!』とは思っていました。
それで、何とかして盛りあげないと!と思って、無理をした部分もあります。
「交流会」の部分は、袖の下でも二重底のお饅頭でもありません。
鋭く、ピシパシお願いします。
いいえ、その通り、鋭いです。
今回の舞台!僕が客席から観ていたら、rookie様のように感じていたと思います。
僕自身も稽古中に『このままでいいの?!』とは思っていました。
それで、何とかして盛りあげないと!と思って、無理をした部分もあります。
「交流会」の部分は、袖の下でも二重底のお饅頭でもありません。
鋭く、ピシパシお願いします。
Posted by セバスティアーノ at 2008年09月29日 07:53